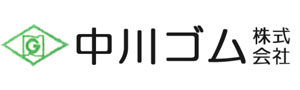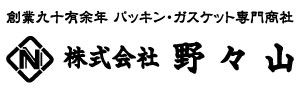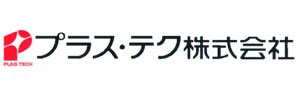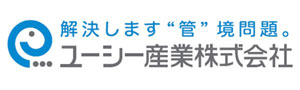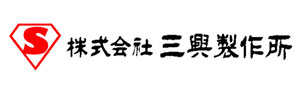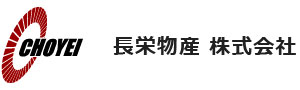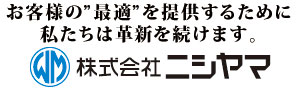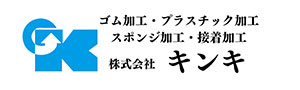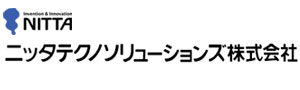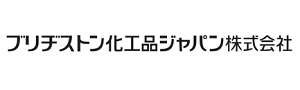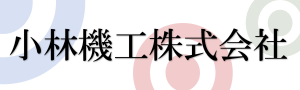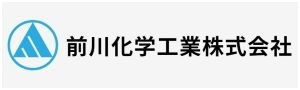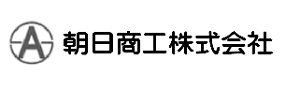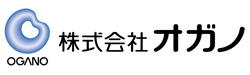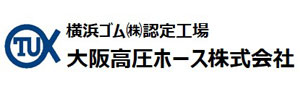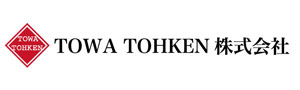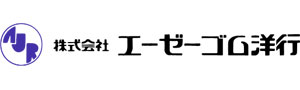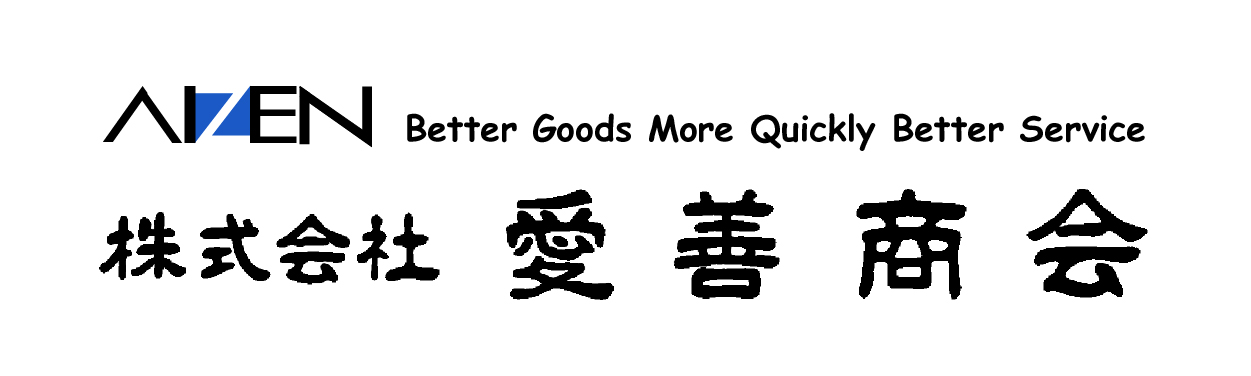ベトナム海外視察研修会レポート
期 間:2025年7月2日~6日
参加者:12名
(特別寄稿 (株)エーゼーゴム洋行 社長 渡辺 周平)
1. はじめに(視察の背景と目的)
2025年7月2日から4日間、西部工業用ゴム製品卸商業組合「次世代経営者の会」主催で有志12名にて、ベトナム(ハノイ・ダナン)への企業視察を実施した。今回の主目的は、同国に進出する日系ゴム関連の優良企業である 住友理工殿・石垣ゴム殿・カテックス殿 の3社を訪問し、製造現場の実態や品質管理手法、人材マネジメントの取り組みを学ぶことにあった。加えて、ベトナムの街並み・生活文化・社会背景を自ら体験することで、将来のビジネス環境を多角的に把握することを狙いとした。
2. ベトナムの国情と現地の印象
関空から約4時間半のフライトでハノイ空港に到着。7月は雨季にあたり、日中の気温は30度前後と比較的過ごしやすいが、湿度が高く体感は重い。空港施設は近代的である一方、外に出れば道路を埋め尽くすバイクの群れ、頻繁に響くクラクション、信号を無視して流れる人と車。都市全体に活気と混沌が共存するエネルギーを感じた。

人口は約1億人、経済成長率は年6%前後と高水準を維持し、特に若年層の厚みが労働市場を支えている。都市部には高層ビルと露天商が同居し、日本の高度成長期を彷彿とさせる。政治体制は一党独裁を維持しつつ市場経済を受容する「安定と開放の並存」が特徴であり、外資にとって安心感のある投資先となっている。
3. 各社訪問記録
3-1 住友理工殿 SumiRiko Vietnam Co.,Ltd
「ベトナム人マネジメントの難しさと“Q・Y・T活動”による品質向上」
工場はハノイから北へ約1.5時間、タンロン工業団地内に位置する。サプライチェーン(供給 網)の多元化・分散化の観点から2022年より稼働を開始した。現在米中貿易摩擦の影響もある ため、地政学的リスクの中で柔軟な生産体制を整えていることがうかがえた。
従業員は300名規模。一般的にベトナム人の賃金は日本の1/3程度でコスト優位性はあるが、 離職率は高水準。人材が豊富な一方で教育負担が重いことから、同社は入社後2週間のカリ キュラムを制度化するなど教育体制を整備している。
特筆すべきは、独自の「QYT活動」(品質不適合予知トレーニング)である。サンプル動画 から標準作業とのズレをチームで指摘し合う仕組みで、KYT(危機予知訓練)を品質管理に 応用した同社独自の活動だ。サンプル動画は実際の作業動画から作成し教材化することで緊張 感を持続させ、改善の自発性を引き出すことに成功している。
さらに、改善提案活動を制度化し、成果を「見える化」することで現場のやる気を醸成して いる。訪問当日もベトナム人従業員が自信をもって成果を発表する姿が印象的であった。日本 とは商習慣やメンタリティーが異なる環境下で、ベトナム人気質に共存するためには努力が必 要と感じた。なお、共通社員旅行や全社ミーティングを定期的に実施するなど、雇用安定化の ための「旧き良き日本的施策」も健在で、組織文化の醸成に工夫を重ねていた。

3-2 石垣ゴム殿 Ishigaki Vietnum Co.,Ltd
「先駆的進出と品質文化の根付かせ方」
ハノイ南方50kmの工業団地に所在。2007年に進出し、2012年に現在地へ移転した。当時、ベトナム進出は一般的ではなく、パイオニア的存在である。特定顧客を見据えたわけではなく、中国工場の社員の強い要望を経営陣が受け止め、果敢に挑戦したと伺った。暗中模索の中で数年以内に黒字化を果たした点は、同社の経営判断と実行力を物語る。
品質面では、中国工場と比べベトナム工場の不適合率は半減。不良発生時には品質部門が徹底的に原因究明を行い、信頼できるベトナム人工場長が現地従業員に噛み砕いて伝えることで改善を定着させている。
一方、離職率は月2〜10%と高く、近隣工場の新設や他社による高額求人広告で流動化しやすい点は大きな課題。社員旅行や家族参加型イベントを必須とし、帰属意識の醸成に努めている。
技術面では、合成ゴム・シリコンを練りから加工まで一貫生産し、約40%がベトナム国内バイクメーカー向け。ゴム配合の誤差を許さないため、人為的ミス防止の仕組みを重層的に設けている。2030年のEV化による需要減少を見据え、多角化が課題となっている。
同社の取り組みは「現地人材の特性を理解し、信頼できる人材を介して品質文化を浸透させる」ことに尽きる。まさにパイオニア精神と堅実な改善活動が結実していた。

3-3 カテックス殿 KTC(Hanoi)Co.,Ltd
「雇用競争とインフラ制約の中での挑戦」
本社は名古屋、ベトナムを含む複数国に拠点を構えるグローバル企業。訪問したのはハノイ東部の工場で、社員数は約280名。本来300〜350名体制を想定するが、人材確保に苦労しており、夏休み中の学生アルバイトや福利厚生イベントを駆使して人材を集めている。
工業団地周辺は外資企業が集中し、「賃金・福利厚生競争」が激化。社員旅行、残業手当、社食の充実、アオザイコンテストまで、あらゆる工夫で人材定着を図っている姿が印象的であった。
インフラ面では電力供給が課題。計画停電や瞬断があり、自家発電設備で補っている。顧客より高精度(0.015mm単位)を要求されるため、ゴム練りやローラー製造工程では全数検査や二重チェック、機械化を徹底。デジタル化に伴う紙需要減少で同社主力製品であるプリンターローラー市場は縮小傾向だが、精密加工技術を他分野に転用することで次の成長を模索している。
中国製品との価格競争では不利な面もあるが、「人件費の安さ」に依存せず、技術力と品質保証で差別化を図る姿勢が印象的であった。

4. ハノイ・ダナンの街並みと文化的所感
ハノイは政治経済の中心であり、フレンチコロニアル建築と現代的高層ビルが混在する。タンロン遺跡、文廟、ホアンキエム湖、旧市街など、歴史的景観と生活空間が一体化している点が特徴的であった。


ダナンは中部最大の都市で、リゾートホテルが立ち並び観光都市として急成長。近隣のホイアン旧市街では提灯の明かりに照らされた歴史的街並みが印象的で、生活文化と観光資源が共存していた。



5. 食事スポット紹介
視察中には地元家庭料理の MOTHER’S KITCHEN、健康志向の Soy Pe PE、ダナンの海沿いで海鮮を楽しめる Brilliant Restaurant、日本食を提供する SAKURA などを利用した。いずれも現地文化を理解する一助となった。



6. 総括と所感
ベトナムは若い労働力、政治の安定、高成長という強みを備える一方で、離職率の高さやインフラ課題など構造的な問題を抱えている。今回訪問した3社はいずれも、日本式の品質管理・改善活動を現地流にアレンジし、根気強く定着させていたことが印象的であった。
人材定着においては「給与」だけでなく「成長機会」「コミュニティ形成」が重要であることを改めて学んだ。街の活気と人々の笑顔は、統計だけでは測れないベトナムの可能性を示すものであった。
本視察は、今後の海外戦略を考える上で多くの示唆を与えてくれる有意義な機会であった。
以上